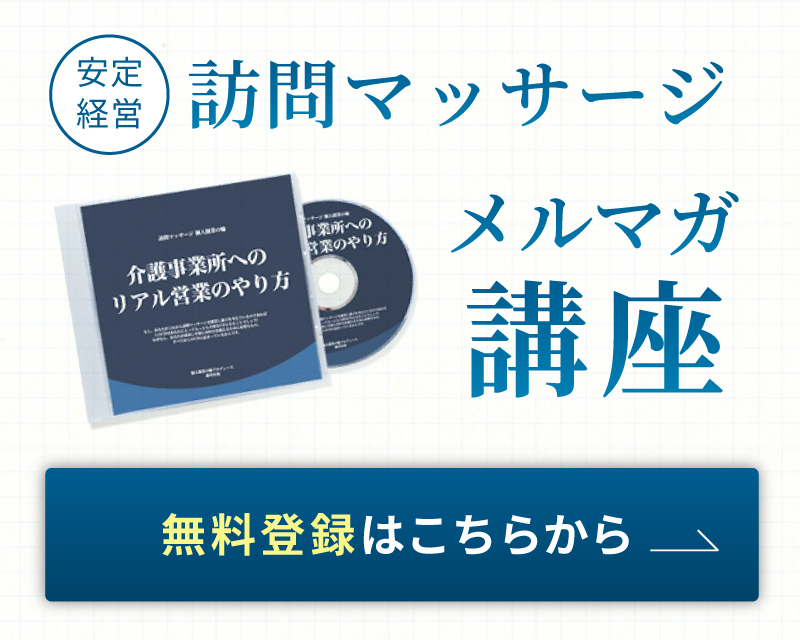こんにちは、
日本訪問マッサージ協会の藤井です。
先日、人気の焼肉屋さんに行ったのですが、
そこのお店は満席で、
各席で楽しそうな飲み会イベントが
行われていました。
お酒が入ると、
普段はなかなか話せないことも気軽に話せるし、
仕事やプライベートの距離が
縮まる良い機会です。
美味しい料理や
お酒を囲んでの場では
意外な一面を知れたり、
新しいアイデアが
生まれたりすることもあります。
訪問マッサージ院でも、
新年会や忘年会やお誕生日会などの
イベントでお酒を飲みながらの
交流の場があると思います。
ただ以前、
訪問マッサージを行うある会社が、
「スタッフ間での飲酒禁止」ルールを
設けていたという話を思い出しました。
僕自身が
その会社の雇用契約書や就業規則を
直接確認したわけではありませんが、
以前、そこで働いていた
鍼灸マッサージ師の話によると、
その会社では確かに
【社員同士の飲酒を禁止】していたそうです。
仕事終わりにスタッフ同士で
飲みに行くことさえ禁止するのは、
少しやり過ぎに思えるかもしれません。
しかし、
その背景には経営者なりの
理由や意図があったと言います。
施術者として働く方々にとって、
職場の同僚と気軽にコミュニケーションを
とれる場は重要です。
「悩みを共有したい」
「営業スタッフや
事務スタッフとも仲良くなりたい」
「愚痴をこぼせる場が欲しい」
といった声も聞こえてきます。
にもかかわらず、
会社がそのような交流を制限するのは、
裏を返せば何かを守るための対策なのです。
考えられる理由として、経営者側が
「スタッフ間の情報共有」によるリスクを
懸念している可能性があります。
具体的には、以下のような
懸念があるのではないでしょうか。
・営業ノウハウの流出
施術者が営業スタッフから得た
ノウハウを活用して
独立開業してしまうリスク。
・事務作業の流出
事務スタッフとの交流で、
社内の書類フォーマットや
事務手続きの知識を吸収されるリスク。
このようなリスクを恐れ、
施術者には施術だけに専念させ、
会社の機密情報を守るために
交流を制限しているのかもしれません。
訪問マッサージの仕事においては、
有資格者である
鍼灸マッサージ師が患者を担当しますが、
患者は施術者個人に対する信頼で
成り立つことが多いため、
施術者が独立開業してしまうと
患者も一緒に移ってしまうケースも
起こりえます。
これは、会社にとっては
損失と言えるかもしれません。
しかし、インターネットが発達し、
AIが発達し、情報が簡単に
共有される現代において、
ノウハウやツールを
完全に「隠す」ことは現実的ではありません。
また、そもそも
「独立開業」を目指す人の
絶対数が
減少傾向にあるというデータもあります。
現在の若い世代の施術者たちは、
以前のように
「独立開業して1000万円を稼ぎたい」
ということを
目標にしない傾向があります。
その代わりに、
「月収30万円、週休2日、社保完備、残業なし」
といった、安定した
労働環境を求める声が増えています。
このニーズに応えることが、
会社としての競争力を
高めるカギになるでしょう。
もちろん、いつの時代においても
独立開業を目指す
施術者は一定数存在します。
そうした人たちに対しては、
会社の営業ノウハウや
事務処理ノウハウを「隠す」のではなく、
むしろ積極的に公開することで、
信頼関係を深めることが大切です。
そして、こう伝えられるような
体制を整えるべきです。
「独立してもいいけど、
独立後も協力し合える関係を築こう」
例えば、独立後も
連携できる仕組みを提供したり、
元スタッフが運営する拠点に
患者を紹介するような仕組みを作るの
一案です。
一方で、施術者が
「この会社で学ぶことはもうない」
と思ってしまうような環境では、
優秀な人材は離れてしまうでしょう。
むしろ、会社の中でキャリアを積み、
自己成長を続けられる
仕組みを用意することが、
離職を防ぐ有効な手段になるはずです。
訪問マッサージや訪問鍼灸は、
施術者という「人材」ありきの
ビジネスモデルです。
施術者なしでは
売上が成り立たない以上、
業界全体としても売上の上限が存在します。
そのため、この上限を突破するような
ビジネスモデルや、
効率的なノウハウを構築することが必要です。
また、優秀な人材が
「この会社で長く働きたい」
と思えるような環境を整えることが、
今後の業界の課題であることは
間違いありません。
これからの時代、
施術者と会社がより良い関係を
築くための新しいルールや
仕組みづくりが求められますね。